詳細
調査を行っ行ったのはアメリカ・ペンシルベニア大学獣医学部のチーム。2008年10月から2010年10月の期間、何らかの問題行動によってペンシルベニア大学マシュー・J・ライアン動物病院の行動医学科を訪れた犬の飼い主を対象とし、飼育放棄(他人への譲渡もしくは安楽死)を考慮するきっかけになる因子が何であるかを検証しました。
合計290頭の犬の飼い主に対し相談に訪れてから10、45、90、180日後のタイミングで追跡調査行い、「相談に訪れる前、犬の安楽死を考えた」、「相談に訪れる前、犬の安楽死もしくは譲渡を考えた」、「相談を受けた後3ヶ月以内に犬を飼育放棄した」、「相談を受けた後6ヶ月以内に犬を飼育放棄した」という4つのカテゴリを設けて統計的に計算したところ、以下のような傾向が浮かび上がってきたといいます。数字は「オッズ比」(OR)で、標準の起こりやすさを「1」としたときどの程度起こりやすいかを相対的に示したものです。数字が1よりも小さければリスクが小さいことを、逆に大きければリスクが大きいことを意味しています。 Dog- and owner-related risk factors for consideration of euthanasia or rehoming before a referral behavior consultation, and for euthanizing or rehoming the dog after the consultation.
Siracusa, C., Provoost, L., Reisner, I.R., Journal of Veterinary Behavior (2017), doi: 10.1016/j.jveb.2017.09.007
合計290頭の犬の飼い主に対し相談に訪れてから10、45、90、180日後のタイミングで追跡調査行い、「相談に訪れる前、犬の安楽死を考えた」、「相談に訪れる前、犬の安楽死もしくは譲渡を考えた」、「相談を受けた後3ヶ月以内に犬を飼育放棄した」、「相談を受けた後6ヶ月以内に犬を飼育放棄した」という4つのカテゴリを設けて統計的に計算したところ、以下のような傾向が浮かび上がってきたといいます。数字は「オッズ比」(OR)で、標準の起こりやすさを「1」としたときどの程度起こりやすいかを相対的に示したものです。数字が1よりも小さければリスクが小さいことを、逆に大きければリスクが大きいことを意味しています。 Dog- and owner-related risk factors for consideration of euthanasia or rehoming before a referral behavior consultation, and for euthanizing or rehoming the dog after the consultation.
Siracusa, C., Provoost, L., Reisner, I.R., Journal of Veterinary Behavior (2017), doi: 10.1016/j.jveb.2017.09.007
相談に訪れる前、犬の安楽死を考えた
増やす要因とオッズ比
- 郊外に暮らしている=2.9
- 獣医師ではない専門家に相談=2.6
- 家族の一員との永続的な別離=2.3
減らす要因とオッズ比
- 恐怖関連行動=0.46
- 家の中に変化なし=0.38
- 皮膚に傷をつけない咬傷=0.35
相談に訪れる前、犬の安楽死もしくは譲渡を考えた
増やす要因とオッズ比
- 獣医師ではない専門家に相談=3.3
- 家族の一員との永続的な別離=3.0
- 独りでいるときに不安兆候を示す=2.6
- リソースガーディング=2.2
減らす要因とオッズ比
- 恐怖関連行動=0.33
- 咬傷歴なし=0.29
相談を受けた後、3ヶ月以内に犬を飼育放棄した
増やす要因とオッズ比
- 常同行動=40.2
- 家庭内に13~17歳の子供がいる=14.0
- 体を触られているときや投薬の際、顔見知りの人に攻撃行動を見せる=10.9
- 犬の入手先が「その他」=6.7
減らす要因とオッズ比
- 恐怖関連行動=0.16
相談を受けた後、6ヶ月以内に犬を飼育放棄した
増やす要因とオッズ比
- 常同行動=7.4
- 痛みに関連した攻撃行動=6.7
- 家庭内に13~17歳の子供がいる=6.5
- 獣医師ではない専門家に相談=5.4
減らす要因とオッズ比
- ブリーダーから入手=0.1
解説
犬や猫の殺処分問題を考えるとき、イギリスやドイツなど動物愛護先進国のお手本として頻繁に引き合いに出される国があります。一部、盲目的に「殺処分が少ない」もしくは「殺処分ゼロ」としてもてはやす人がいますが、こうした国は行政による処分数が少ないという事しか意味していません。飼い主が動物病院に持ち込んで行う安楽死まで含めて考えないと、真の意味での殺処分問題を考えているとは言えないでしょう。
例えば1998年、イギリス国内で開業している動物病院を対象として行った調査では、安楽死を受けた犬のうち問題行動に原因があるものは全体の5.9%だったとされています(Edney, 1998)。また2003年にデンマークで行われた調査では、安楽死のうち犬の問題行動が原因だったものは6.4%だったとも(Proschowsky et al., 2003)。今後、欧米諸国を動物福祉のお手本として引き合いに出すときは、飼い主が臨床上健康な犬に対して行う安楽死の数も含めて考慮しないと、理想的とはいえない国を教科書にしてしまうことになりかねません。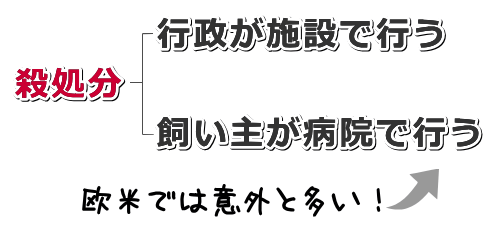 今回の調査対象となった290頭の犬に関し、平均年齢は46.8ヶ月齢(4歳弱)、平均体重は23.2kg、純血種は61%(178頭)、ペットショップでの入手は8%(23頭)という内訳でした。ペットショップを経由して購入される小型犬が多い日本とは統計的な下地がずいぶん異なるため、当調査のデータをそっくりそのまま輸入するわけにはいきません。しかしいくつかヒントになる項目があります。
今回の調査対象となった290頭の犬に関し、平均年齢は46.8ヶ月齢(4歳弱)、平均体重は23.2kg、純血種は61%(178頭)、ペットショップでの入手は8%(23頭)という内訳でした。ペットショップを経由して購入される小型犬が多い日本とは統計的な下地がずいぶん異なるため、当調査のデータをそっくりそのまま輸入するわけにはいきません。しかしいくつかヒントになる項目があります。
例えば1998年、イギリス国内で開業している動物病院を対象として行った調査では、安楽死を受けた犬のうち問題行動に原因があるものは全体の5.9%だったとされています(Edney, 1998)。また2003年にデンマークで行われた調査では、安楽死のうち犬の問題行動が原因だったものは6.4%だったとも(Proschowsky et al., 2003)。今後、欧米諸国を動物福祉のお手本として引き合いに出すときは、飼い主が臨床上健康な犬に対して行う安楽死の数も含めて考慮しないと、理想的とはいえない国を教科書にしてしまうことになりかねません。
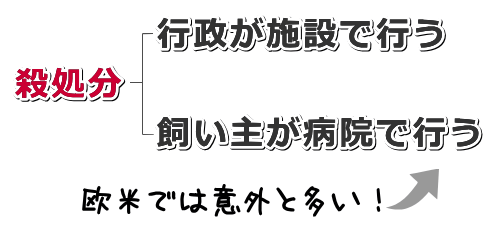 今回の調査対象となった290頭の犬に関し、平均年齢は46.8ヶ月齢(4歳弱)、平均体重は23.2kg、純血種は61%(178頭)、ペットショップでの入手は8%(23頭)という内訳でした。ペットショップを経由して購入される小型犬が多い日本とは統計的な下地がずいぶん異なるため、当調査のデータをそっくりそのまま輸入するわけにはいきません。しかしいくつかヒントになる項目があります。
今回の調査対象となった290頭の犬に関し、平均年齢は46.8ヶ月齢(4歳弱)、平均体重は23.2kg、純血種は61%(178頭)、ペットショップでの入手は8%(23頭)という内訳でした。ペットショップを経由して購入される小型犬が多い日本とは統計的な下地がずいぶん異なるため、当調査のデータをそっくりそのまま輸入するわけにはいきません。しかしいくつかヒントになる項目があります。
郊外に暮らしている
郊外に暮らしている場合、都市部に暮らしている人よりも3倍ほど犬の譲渡や安楽死を考慮する確率が高いことが明らかになりました。この傾向の背景にあるのは、犬を家族の一員というよりも使役犬(番犬など)としてみなす風土だと推測されます。そしてこの傾向は日本においてもあるかもしれません。
例えば兵庫県の動物愛護センター淡路支所は、管轄区域内の人口割合が県の5%程度しかないにもかかわらず、平成28年度に収容された犬473頭のうち26%を占めていたと言います(→出典)。こうした偏った比率が生じる原因としては、放し飼いの習慣や出産管理の不徹底などが想定されています。この事実から見えてくるのは、犬は家族ではなくあくまでも動物という「たかがワン公意識」→監督不行き届き→飼育放棄・収容・殺処分という因果関係です。犬を家族ではなく所有物としてみなしている分、手放す時の精神的な抵抗が少なくなるということは大いにあるでしょう。
例えば兵庫県の動物愛護センター淡路支所は、管轄区域内の人口割合が県の5%程度しかないにもかかわらず、平成28年度に収容された犬473頭のうち26%を占めていたと言います(→出典)。こうした偏った比率が生じる原因としては、放し飼いの習慣や出産管理の不徹底などが想定されています。この事実から見えてくるのは、犬は家族ではなくあくまでも動物という「たかがワン公意識」→監督不行き届き→飼育放棄・収容・殺処分という因果関係です。犬を家族ではなく所有物としてみなしている分、手放す時の精神的な抵抗が少なくなるということは大いにあるでしょう。
獣医師ではない専門家に相談
獣医師ではない専門家(ドッグトレーナーや動物行動医学者)に相談したことがある人ほど、犬の飼育放棄を事前に考慮したり、3ヵ月後のタイミングで実際に飼育放棄する確率が高くなることが明らかになりました。
まず考えられる可能性は、専門家と称する人が資質に欠けており、まるでどこかのヨットスクールのように罰を用いたトレーニングや行動矯正を飼い主に指示し、結果として犬のストレスと問題行動の悪化を招いて飼育放棄につながったというものです。統計的に有意とまでは判断されなかったものの、罰ベースのしつけ方法を採用している飼い主の方が、ご褒美ベースのしつけ方法を採用している飼い主よりも犬を飼育放棄しやすい傾向が認めらたことからも、上記した因果関係が伺えます。
考えられるもう一つの可能性は、「専門家に相談するほどそもそも犬の問題行動が深刻だった」というものです。この場合、専門家に相談したことが飼育放棄を招いたわけではなく、飼い主もしくは犬の側に原因があって飼育放棄につながったということになります。
まず考えられる可能性は、専門家と称する人が資質に欠けており、まるでどこかのヨットスクールのように罰を用いたトレーニングや行動矯正を飼い主に指示し、結果として犬のストレスと問題行動の悪化を招いて飼育放棄につながったというものです。統計的に有意とまでは判断されなかったものの、罰ベースのしつけ方法を採用している飼い主の方が、ご褒美ベースのしつけ方法を採用している飼い主よりも犬を飼育放棄しやすい傾向が認めらたことからも、上記した因果関係が伺えます。
考えられるもう一つの可能性は、「専門家に相談するほどそもそも犬の問題行動が深刻だった」というものです。この場合、専門家に相談したことが飼育放棄を招いたわけではなく、飼い主もしくは犬の側に原因があって飼育放棄につながったということになります。
家族の一員との永続的な別離
家族の一員との永続的な別離を経験した犬の方が、飼育放棄の対象になりやすいことが明らかになりました。別れた家族の一員が犬の世話を担当していた場合、別離に付随して犬の世話がおろそかになり、ストレスの増大から問題行動が引き起こされた可能性があります。あるいは単純に愛着を抱いていた人との別離が犬にとってのストレスとなり、無駄吠えや常同行動といった行動として現れ、それが残された家族の気に障ったのかもしれません。
常同行動
同じ行動を無目的に繰り返す「常同行動」を示す犬は、3ヶ月後の飼育放棄リスクが40倍、6ヶ月後のリスクが7倍に高まる傾向が確認されました。同じ場所を行ったり来たりするといったパターンの場合はそれほど実害はありませんが、前足の特定部分を延々となめ続けるといったパターンの場合は、ときとして医療問題に発展し、飼い主に心理的・経済的な負担を強いてしまいます。加えて犬自身の健康も悪化するため、「いっそのこと楽にしてあげよう」という動機が生まれやすくなってしまうのでしょうか。
家庭内に13~17歳の子供がいる
13~17歳の子供がいる家庭においては、犬が飼育放棄されてしまうリスクが3ヶ月後で14倍、6ヶ月後で6.5倍に高まることが確認されました。理由としては「思春期の子供に時間を取られ、親が十分に犬の世話ができない」、「子供が思春期になると、以前ほど犬をかまわなくなる」などが考えられます。いずれにしても、犬に対して投資する時間が減るため、ストレスの増大から問題行動につながってしまう可能性を否定できません。
攻撃行動
体を触られているときや投薬の際、顔見知りの人に攻撃行動を見せる犬は3ヶ月後の飼育放棄リスクが10.9倍、また痛みに関連した攻撃行動を見せる犬は6ヶ月後のリスクが6.7倍に高まってしまうようです。犬が見せる攻撃行動はそれだけで十分に飼育放棄の原因になりますが、そこに「投薬を必要とするような病気を患っている」とか「痛みを抱えている」といった要因が加わると、飼い主が飼育放棄を決断しやすくなってしまうものと推測されます。


