伝説の出どころ
「犬は人間と共に進化してきた」という都市伝説の出どころは、オーストラリア国立大学の著名な自然人類学者コリン・グローヴス教授が主張した「人間は犬を家畜化し、犬は人間を家畜化した」という説だと考えられます(→出典)。彼によると、原始の犬は人間の警告システム、追跡や狩猟の相棒、残飯処理係、湯たんぽ、子守、遊び相手となる代わりに、人間から食料と安全を与えられるような存在だったとしています。つまり、人間と犬はお互いの存在に依存しながら共に進化してきたと言うわけです。
彼の説を裏付けるかような調査報告もあります。2004年、スウェーデンの研究チームは、さまざまな構成人数から成る4つのハンターグループを用意し、「犬がいる」と「犬がいない」というバリエーションを設けて狩猟の成功率を比較しました(→出典)。その結果、どのグループサイズにおいても犬がいる方が高い成功率を収めたといいます。さらにグループの構成人数が10人未満の小グループでは成績が1.5倍になり、10人より多い人数で構成されているグループでも、犬の数が増えるほど、狩猟の成功率も高まったとのこと。こうしたデータから研究チームは、狼を家畜化する過程で、犬のもつ狩猟パートナーとしての役割は、決定的に重要だったに違いないとの結論に至りました。 上記グローヴス教授の他にも、「ゾウがすすり泣くとき」や「犬の愛に嘘はない」(共に河出書房新社)などの著作で知られるアメリカ人作家ジェフリー・M・マッソンは、「ヒトはイヌのおかげで人間になった」(飛鳥新社)の中で「イヌトヒトとは種としてのそれぞれの成長期間を重大な時期に共進化した。イヌがいたからこそ、人間は人間らしい人間になったのだ」とし、犬と人間の共進化説を支持しています。
上記グローヴス教授の他にも、「ゾウがすすり泣くとき」や「犬の愛に嘘はない」(共に河出書房新社)などの著作で知られるアメリカ人作家ジェフリー・M・マッソンは、「ヒトはイヌのおかげで人間になった」(飛鳥新社)の中で「イヌトヒトとは種としてのそれぞれの成長期間を重大な時期に共進化した。イヌがいたからこそ、人間は人間らしい人間になったのだ」とし、犬と人間の共進化説を支持しています。
さらに近年は、アメリカの人類学者パット・ シップマンが「ヒトとイヌがネアンデルタール人を絶滅させた」(原書房)という書物の中で、「私たち人類の祖先である現生人類が繁栄し、ネアンデルタール人が滅びた背景には、犬の存在がある」という主張を展開し、人間と犬とがともに支え合いながら生存競争を勝ち抜いてきたという人類史観を明らかにしました。
このように「犬と人間は共に進化してきた」という考え方は、一部の人の間で広く信じられているようです。この事実は、1789年にプロイセン王が最初に考案したとされる、誰もが一度は耳にしたことがあるフレーズ「犬は人類にとって最良の友」(Dog is Man's best friend)の中に集約されています。
彼の説を裏付けるかような調査報告もあります。2004年、スウェーデンの研究チームは、さまざまな構成人数から成る4つのハンターグループを用意し、「犬がいる」と「犬がいない」というバリエーションを設けて狩猟の成功率を比較しました(→出典)。その結果、どのグループサイズにおいても犬がいる方が高い成功率を収めたといいます。さらにグループの構成人数が10人未満の小グループでは成績が1.5倍になり、10人より多い人数で構成されているグループでも、犬の数が増えるほど、狩猟の成功率も高まったとのこと。こうしたデータから研究チームは、狼を家畜化する過程で、犬のもつ狩猟パートナーとしての役割は、決定的に重要だったに違いないとの結論に至りました。
 上記グローヴス教授の他にも、「ゾウがすすり泣くとき」や「犬の愛に嘘はない」(共に河出書房新社)などの著作で知られるアメリカ人作家ジェフリー・M・マッソンは、「ヒトはイヌのおかげで人間になった」(飛鳥新社)の中で「イヌトヒトとは種としてのそれぞれの成長期間を重大な時期に共進化した。イヌがいたからこそ、人間は人間らしい人間になったのだ」とし、犬と人間の共進化説を支持しています。
上記グローヴス教授の他にも、「ゾウがすすり泣くとき」や「犬の愛に嘘はない」(共に河出書房新社)などの著作で知られるアメリカ人作家ジェフリー・M・マッソンは、「ヒトはイヌのおかげで人間になった」(飛鳥新社)の中で「イヌトヒトとは種としてのそれぞれの成長期間を重大な時期に共進化した。イヌがいたからこそ、人間は人間らしい人間になったのだ」とし、犬と人間の共進化説を支持しています。さらに近年は、アメリカの人類学者パット・ シップマンが「ヒトとイヌがネアンデルタール人を絶滅させた」(原書房)という書物の中で、「私たち人類の祖先である現生人類が繁栄し、ネアンデルタール人が滅びた背景には、犬の存在がある」という主張を展開し、人間と犬とがともに支え合いながら生存競争を勝ち抜いてきたという人類史観を明らかにしました。
このように「犬と人間は共に進化してきた」という考え方は、一部の人の間で広く信じられているようです。この事実は、1789年にプロイセン王が最初に考案したとされる、誰もが一度は耳にしたことがあるフレーズ「犬は人類にとって最良の友」(Dog is Man's best friend)の中に集約されています。
伝説の検証
犬と人間がともに進化してきたのならば、両者の間に収斂進化の証拠があるはずだという考え方があります。「収斂進化」(しゅうれんしんか)とは、異なる種類の動物がそれぞれ独立した状態で進化したにも関わらず、ある種の問題に対して同じ解決法や解決能力を獲得する現象のことです。例えば、ペンギンとイルカはそれぞれ独立した種として進化してしましたが、「水中で暮らす」という共通の問題に対し、「ヒレを持つ」という収斂進化で対応しています。
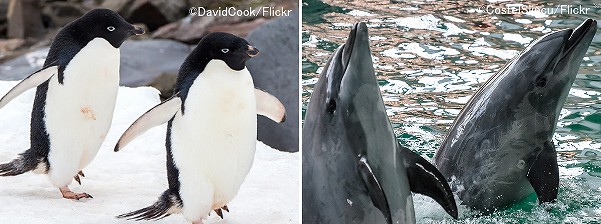 一方、犬と人間とを見比べたとき、見た目が全く違うため完全に別々の動物だと判断してしまいそうになります。しかしよくよく調べてみると、「収斂進化の痕跡ではないか?」と思われるような部分がちらほら見受けられます。具体的には以下です。
一方、犬と人間とを見比べたとき、見た目が全く違うため完全に別々の動物だと判断してしまいそうになります。しかしよくよく調べてみると、「収斂進化の痕跡ではないか?」と思われるような部分がちらほら見受けられます。具体的には以下です。
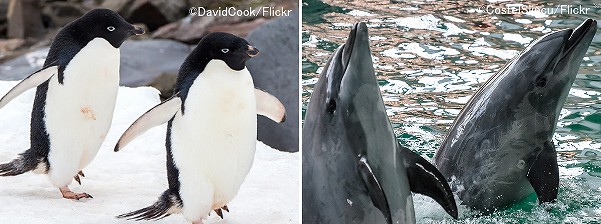 一方、犬と人間とを見比べたとき、見た目が全く違うため完全に別々の動物だと判断してしまいそうになります。しかしよくよく調べてみると、「収斂進化の痕跡ではないか?」と思われるような部分がちらほら見受けられます。具体的には以下です。
一方、犬と人間とを見比べたとき、見た目が全く違うため完全に別々の動物だと判断してしまいそうになります。しかしよくよく調べてみると、「収斂進化の痕跡ではないか?」と思われるような部分がちらほら見受けられます。具体的には以下です。
収斂進化の証拠・目次
デンプン分解能
近年、「AMY2B」という遺伝子に関し、犬は狼よりもたくさんのコピーナンバー数を有していることが明らかになりました。「AMY2B」とはデンプンの分解能力に関わる遺伝子のことで、コピーナンバーが多ければ多いほど分解能力が高いことを意味しています。そしてこの「デンプン分解能」が、犬と人間の収斂進化を示す確たる証拠ではないかという考え方がにわかに浮上してきました。
犬のデンプン分解能
- Axelssonらの調査(2013年) 犬と狼を対象としてゲノム解析を行い、380万の遺伝的変異体の中から、家畜化以降に出現したと思われる36の区画を抽出して比較した。その結果、19は脳の機能に、8は神経系の発達に、そして10はデンプンの分解と脂質の代謝に関係していることが明らかになった。犬が狼よりも高いデンプン分解能を有しているという事実は、彼らが雑食である人間と長い間ともに暮らしてきたことを意味しているかもしれない(→出典)。
- Freedmanらの調査(2013) 狼では「AMY2B」のコピーナンバーの数に大きな個体差がある。一方、遺伝的に狼に近いとされるディンゴやハスキーでは、コピーナンバー数の増加が全く見られないか、あってもわずかである。犬と狼の分岐時期を逆算すると、従来の定説とは異なり、犬は農耕を開始した頃の人間とではなく、まだ狩猟採集民だった頃の人間と共に生きてきた可能性がある(→出典)。
- Arendtらの調査(2014年) 人間においては、「AMY1」という遺伝子が唾液中のアミラーゼレベルと酵素活性に影響を及ぼすことが分かっている。20犬種を対象として「AMY2B」のコピーナンバー数を調べたところ、犬種によって大きな開きがあり、デンプンの分解能に影響を及ぼしていることが分かった(→出典)。
- Tonoikeらの調査(2015年) 日本の古来種と考えられている秋田犬と柴犬のDNAを解析し、アミラーゼの生成に関わる「AMY2B」という遺伝子を、オオカミやヨーロッパ原産種と比較した。その結果、デンプン分解能に関し「ヨーロッパ原産種・柴犬 >秋田犬・縄文柴 >オオカミ」という順になった。犬種間で見られるデンプン分解能力の差は、それぞれの犬種が発祥した土地における、稲作の導入時期の時間差を反映しているのではないか(→出典)。
ジェスチャー理解力
アメリカの比較人類学者ブライアン・ヘア氏は、指示ジェスチャーに対する理解力が犬と人間の「認知的収斂進化」を示しているのではないかという仮説を提唱しています(→出典)。
指示ジェスチャーとは、何らかの指示を出すことにより、相手の注意をターゲットに向ける動作のことです。具体的には「指先で示す」、「見つめる」、「ターゲットの上でお辞儀をしたり頷く」、「ターゲットの上に印をつける」といった例があります。人間では早くも生後14ヶ月頃からジェスチャーの意味を理解出来るようになり、犬では生後9週齢くらいから理解を示すようになるといいます。この能力は、犬が人間と暮らしたことがあろうがなかろうが、ペット犬だろうが野生種に近いニューギニアシンギングドッグだろうが変わらないとのこと。 一方、犬の祖先とされている狼で能力をテストしたところ、ジェスチャーの意味を理解するのに非常に長い時間を要し、犬と同じレベルになったのは生後11ヶ月の頃だったそうです。さらに、遺伝的には犬よりもはるかに人間に近いチンパンジーに対して同じテストを行ったところ、人間と生活を共にしてきた個体以外は非常に成績が悪く、一つのジェスチャーを理解させるのに何十回も試行錯誤を繰り返さなければならなかったかったと言います。
一方、犬の祖先とされている狼で能力をテストしたところ、ジェスチャーの意味を理解するのに非常に長い時間を要し、犬と同じレベルになったのは生後11ヶ月の頃だったそうです。さらに、遺伝的には犬よりもはるかに人間に近いチンパンジーに対して同じテストを行ったところ、人間と生活を共にしてきた個体以外は非常に成績が悪く、一つのジェスチャーを理解させるのに何十回も試行錯誤を繰り返さなければならなかったかったと言います。
ヘア氏は、犬と人間が共有している「相手のジェスチャーをメッセージとして理解する」という能力は、両者が長い間同じ環境で暮らしてきた結果として起こった収斂進化の一例ではないかと結論づけました。 あなたの犬は「天才」だ(ハヤカワ・ノンフィクション)
指示ジェスチャーとは、何らかの指示を出すことにより、相手の注意をターゲットに向ける動作のことです。具体的には「指先で示す」、「見つめる」、「ターゲットの上でお辞儀をしたり頷く」、「ターゲットの上に印をつける」といった例があります。人間では早くも生後14ヶ月頃からジェスチャーの意味を理解出来るようになり、犬では生後9週齢くらいから理解を示すようになるといいます。この能力は、犬が人間と暮らしたことがあろうがなかろうが、ペット犬だろうが野生種に近いニューギニアシンギングドッグだろうが変わらないとのこと。
 一方、犬の祖先とされている狼で能力をテストしたところ、ジェスチャーの意味を理解するのに非常に長い時間を要し、犬と同じレベルになったのは生後11ヶ月の頃だったそうです。さらに、遺伝的には犬よりもはるかに人間に近いチンパンジーに対して同じテストを行ったところ、人間と生活を共にしてきた個体以外は非常に成績が悪く、一つのジェスチャーを理解させるのに何十回も試行錯誤を繰り返さなければならなかったかったと言います。
一方、犬の祖先とされている狼で能力をテストしたところ、ジェスチャーの意味を理解するのに非常に長い時間を要し、犬と同じレベルになったのは生後11ヶ月の頃だったそうです。さらに、遺伝的には犬よりもはるかに人間に近いチンパンジーに対して同じテストを行ったところ、人間と生活を共にしてきた個体以外は非常に成績が悪く、一つのジェスチャーを理解させるのに何十回も試行錯誤を繰り返さなければならなかったかったと言います。ヘア氏は、犬と人間が共有している「相手のジェスチャーをメッセージとして理解する」という能力は、両者が長い間同じ環境で暮らしてきた結果として起こった収斂進化の一例ではないかと結論づけました。 あなたの犬は「天才」だ(ハヤカワ・ノンフィクション)
愛着の形成
犬と人間の間に形成される愛着関係が、両者の収斂進化を示しているのではないかという考え方があります。この考え方を理解するためには、まず前置きとして「愛着理論」について知っておかなければなりません。
愛着理論とは?
「愛着理論」とは、子供が正常に発達するためには「安全基地」となる養育者との親密な関係が必要であり、これがないと後に社会的な問題を抱えるようになるとする考え方のことです。人間においては、一般的には以下のような順を追って発達すると考えられています。
人間における愛着の発達
- 生後8週まで 乳児は養育者の注意を引くために、微笑んだり、声を出したり、泣いたりするが、養育者と非養育者の区別は不明瞭。
- 生後2~6ヶ月 乳児は養育者と非養育者を区別できるようになり、前者に対してより強い反応を示すようになる。
- 6ヶ月~2歳 幼児は養育者に対して明確な愛着行動を示すようになる。例えば、養育者がいなくなると不安になり、養育者が戻ってくるとまとわり付いたりするなど。また養育者を「安全基地」とみなすようになり、近くに養育者がいる場合は安心して周囲を探索するものの、いない場合は不安になっておとなしくなる。
ストレンジシチュエーション
- ステップ1(1分)実験室内に子供と親が入室する
- ステップ2(2分)子供に自由に室内探索させる
- ステップ3(3分)見知らぬ第三者が入室して親と会話し、その後子供に近づく
- ステップ4(3分)親はこっそりと退室し、残された第三者は子供に合わせて行動する(第一の別離)
- ステップ5(3分)親が再び入室し、子供に挨拶する。第三者はこっそりと退室する(第一の再会)
- ステップ6(3分)親が退室し、子供は室内にひとりぼっちになる(第二の別離)
- ステップ7(3分)第三者が入室し、子供に合わせて行動する
- ステップ8(3分)親が入室し、第三者はこっそり退室する(第二の再会)
犬と愛着理論
人間の親子の間で見られる愛着関係が犬と飼い主との間で見られる愛着関係と同じものであるという仮定の下、「ストレンジシチュエーション」を犬用に微調整したテストを用い、様々な実証実験が行われてきました。下に列挙するのはほんの一例ですが、犬を対象とした同種の実験では概ね犬は人間の幼児や人間に育てられたチンパンジーが見せるのと同じような愛着を人間に対して抱いているようだとの結論に至っています。
 子供と養育者との間の愛着を定義した最初の研究者であるジョン・ボウルビィは、愛着と養育は哺乳類と多くの鳥類における子育てのための行動システムであり、子どもの生存確率を増加させ、結果として親に健康の恩恵をもたらすと述べています。またアメリカ・メリーランド大学の心理学者ジュード・キャシディは、子供が養育者に対して抱く感情的な愛着は進化的なプレッシャーによって形成された可能性があると指摘しています(→出典)。つまり、自分を養育してくれる人に対し愛着を抱くことにより、心身ともに不安定な乳幼児期を乗り切りやすくなったということです。もし犬が、他の動物種では見られないような強い愛着行動を人間に示すことによって養育本能を刺激し、自身の生存確率を高めるよう進化してきたのだったら、それは収斂進化の一つの形態と言えるかもしれません。ただし人間との決定的な違いは、犬の愛着行動は子犬の時期が終わってからもずっと継続するという点です。
子供と養育者との間の愛着を定義した最初の研究者であるジョン・ボウルビィは、愛着と養育は哺乳類と多くの鳥類における子育てのための行動システムであり、子どもの生存確率を増加させ、結果として親に健康の恩恵をもたらすと述べています。またアメリカ・メリーランド大学の心理学者ジュード・キャシディは、子供が養育者に対して抱く感情的な愛着は進化的なプレッシャーによって形成された可能性があると指摘しています(→出典)。つまり、自分を養育してくれる人に対し愛着を抱くことにより、心身ともに不安定な乳幼児期を乗り切りやすくなったということです。もし犬が、他の動物種では見られないような強い愛着行動を人間に示すことによって養育本能を刺激し、自身の生存確率を高めるよう進化してきたのだったら、それは収斂進化の一つの形態と言えるかもしれません。ただし人間との決定的な違いは、犬の愛着行動は子犬の時期が終わってからもずっと継続するという点です。
犬と愛着の実証実験
- Topalらの調査(1998年) 犬と飼い主のペア51組を対象とし、犬用にアレンジした「ストレンジシチュエーション」を実施した。その結果、犬はチンパンジーや人間の幼児が親に対して見せるのと同じ愛着行動を示した(→出典)。
- Prato-Prevideらの調査(2003年) 飼い主と犬のペア38組に対し、人間で用いられるテストに限りなく近づけた「ストレンジシチュエーション」を実施した。その結果、犬たちは飼い主がいなくなると「吠える」、「ドアの方をじっと見る」、「ドアを引っ掻く」といった不安行動を見せ、飼い主と再会した際は「あいさつする」、「飛びつく」、「後をついて回る」といった典型的な愛着行動を見せた。また飼い主が近くにいる時の方が、見知らぬ第三者と遊ぶ傾向が強まった。犬は飼い主の事を安全基地と見なしているようだが、「別離」と「再会」の順番が疲労や慣れを招き、結果に影響を及ぼしている可能性は否定できない(→出典)。
- Palmerらの調査(2008年) 犬と飼い主のペア38組を対象に「ストレンジシチュエーション」を犬向けにアレンジしたテストを行った。「状況1」では「犬と飼い主が見知らぬ部屋に入室する→第三者が入室する→飼い主が退室する→飼い主が戻る→飼い主が再び退室する」という流れで行い、「状況2」では「犬と第三者が見知らぬ部屋に入室する→飼い主が入室する→第三者が退出する→第三者が戻る→第三者が再び退室する」という真逆の流れで行った。その結果、どちらの状況においても飼い主が身近にいる時の方がより受身的(落ち着いた状態のこと)で、第三者と遊んだり、ひとりで遊んだりする行動が多く観察された。これは犬が飼い主のことを「安全基地」とみなしている証拠だと推測される(→出典)。
 子供と養育者との間の愛着を定義した最初の研究者であるジョン・ボウルビィは、愛着と養育は哺乳類と多くの鳥類における子育てのための行動システムであり、子どもの生存確率を増加させ、結果として親に健康の恩恵をもたらすと述べています。またアメリカ・メリーランド大学の心理学者ジュード・キャシディは、子供が養育者に対して抱く感情的な愛着は進化的なプレッシャーによって形成された可能性があると指摘しています(→出典)。つまり、自分を養育してくれる人に対し愛着を抱くことにより、心身ともに不安定な乳幼児期を乗り切りやすくなったということです。もし犬が、他の動物種では見られないような強い愛着行動を人間に示すことによって養育本能を刺激し、自身の生存確率を高めるよう進化してきたのだったら、それは収斂進化の一つの形態と言えるかもしれません。ただし人間との決定的な違いは、犬の愛着行動は子犬の時期が終わってからもずっと継続するという点です。
子供と養育者との間の愛着を定義した最初の研究者であるジョン・ボウルビィは、愛着と養育は哺乳類と多くの鳥類における子育てのための行動システムであり、子どもの生存確率を増加させ、結果として親に健康の恩恵をもたらすと述べています。またアメリカ・メリーランド大学の心理学者ジュード・キャシディは、子供が養育者に対して抱く感情的な愛着は進化的なプレッシャーによって形成された可能性があると指摘しています(→出典)。つまり、自分を養育してくれる人に対し愛着を抱くことにより、心身ともに不安定な乳幼児期を乗り切りやすくなったということです。もし犬が、他の動物種では見られないような強い愛着行動を人間に示すことによって養育本能を刺激し、自身の生存確率を高めるよう進化してきたのだったら、それは収斂進化の一つの形態と言えるかもしれません。ただし人間との決定的な違いは、犬の愛着行動は子犬の時期が終わってからもずっと継続するという点です。
他の動物と愛着理論
「ストレンジシチュエーション」を犬以外の動物に適応した例もあります。しかし犬が見せるような明確な愛着行動は確認されませんでした。この事実から「こうした動物たちには愛着がまるでない」とまでは言い切れませんが、犬という動物がいかに特異な存在であるかを実感する手掛かりにはなるでしょう。
犬以外の動物と愛着
- 狼(Topalらの調査, 2005年) 全く同じ環境で育てられた子犬と子狼を対象に、4ヶ月齢になったタイミングで「ストレンジシチュエーション」を実施した。その結果、子犬たちが見知らぬ人間よりも養育者に対して強い愛着行動を示したのに対し、狼の方は養育者と第三者をそれほど区別しなかった。犬と狼との間には、愛着形成過程に決定的な違いがあるものと推測される(→出典)。
- 猫(Potterらの調査, 2015) 「ストレンジシチュエーション」を猫用にアレンジし、猫と飼い主の間にある愛着関係を検証した。18組のペアを観察した結果、「飼い主が部屋から出ていくという状況で鳴く頻度が増える」という項目以外、猫と飼い主の間の愛着を示す証拠は何一つ見つからなかった。猫は、人間の子供や犬のように保護者(親や飼い主)を「安全基地」とはとらえていないのかもしれない(→出典)。
伝説の結論
近年、犬と人間は従来よりもかなり古い1万8,800~3万2,000年前頃から共に暮らしてきたのではないかという仮説が検証されています。もし犬と人間が2~3万年という長い年月を似たような環境の中で暮らしてきたとするならば、「限られた食料を最大限に生かす」、「相手のジェスチャーをすばやく理解して狩猟の成功率を高める」、「養育者に愛着を示して生存確率を高める」といった共通の課題を抱えるようになってもおかしくはありません。そしてそれぞれに対応した収斂進化が「デンプン分解能」、「ジェスチャー理解力」、「愛着の形成」だという考え方にはそれなりの説得力があります。ですから「犬と人間は共に進化してきた」という都市伝説は大いにあり得ると考えて良いでしょう。
 2014年、異なる高度に暮らしている犬と人間を対象とし、血液中のヘモグロビンレベルを比較するという調査が行われました(→出典)。その結果、中国の低地よりもチベット平原に暮らしている人間と犬のヘモグロビンレベルの方が高かったと言います。「酸素濃度が低い」という問題に対し、犬と人間が同じように「ヘモグロビンレベルを高める」という解決法で対処したことを示す一例です。血液の組成は一時的なもので遺伝的に固定された「進化」とは呼べないかもしれません。しかし、同じ環境に暮らしている場合、たとえ生物学的にはまったく異なる動物同士でも、最終的には同じ能力を身につけることを示す好例と言えるでしょう。私たち人間と犬との間には、見た目だけからはわからないさまざまな収斂進化の痕跡が、遺伝子という膨大な海の中にまだ隠されているのかもしれません。
2014年、異なる高度に暮らしている犬と人間を対象とし、血液中のヘモグロビンレベルを比較するという調査が行われました(→出典)。その結果、中国の低地よりもチベット平原に暮らしている人間と犬のヘモグロビンレベルの方が高かったと言います。「酸素濃度が低い」という問題に対し、犬と人間が同じように「ヘモグロビンレベルを高める」という解決法で対処したことを示す一例です。血液の組成は一時的なもので遺伝的に固定された「進化」とは呼べないかもしれません。しかし、同じ環境に暮らしている場合、たとえ生物学的にはまったく異なる動物同士でも、最終的には同じ能力を身につけることを示す好例と言えるでしょう。私たち人間と犬との間には、見た目だけからはわからないさまざまな収斂進化の痕跡が、遺伝子という膨大な海の中にまだ隠されているのかもしれません。
 2014年、異なる高度に暮らしている犬と人間を対象とし、血液中のヘモグロビンレベルを比較するという調査が行われました(→出典)。その結果、中国の低地よりもチベット平原に暮らしている人間と犬のヘモグロビンレベルの方が高かったと言います。「酸素濃度が低い」という問題に対し、犬と人間が同じように「ヘモグロビンレベルを高める」という解決法で対処したことを示す一例です。血液の組成は一時的なもので遺伝的に固定された「進化」とは呼べないかもしれません。しかし、同じ環境に暮らしている場合、たとえ生物学的にはまったく異なる動物同士でも、最終的には同じ能力を身につけることを示す好例と言えるでしょう。私たち人間と犬との間には、見た目だけからはわからないさまざまな収斂進化の痕跡が、遺伝子という膨大な海の中にまだ隠されているのかもしれません。
2014年、異なる高度に暮らしている犬と人間を対象とし、血液中のヘモグロビンレベルを比較するという調査が行われました(→出典)。その結果、中国の低地よりもチベット平原に暮らしている人間と犬のヘモグロビンレベルの方が高かったと言います。「酸素濃度が低い」という問題に対し、犬と人間が同じように「ヘモグロビンレベルを高める」という解決法で対処したことを示す一例です。血液の組成は一時的なもので遺伝的に固定された「進化」とは呼べないかもしれません。しかし、同じ環境に暮らしている場合、たとえ生物学的にはまったく異なる動物同士でも、最終的には同じ能力を身につけることを示す好例と言えるでしょう。私たち人間と犬との間には、見た目だけからはわからないさまざまな収斂進化の痕跡が、遺伝子という膨大な海の中にまだ隠されているのかもしれません。


